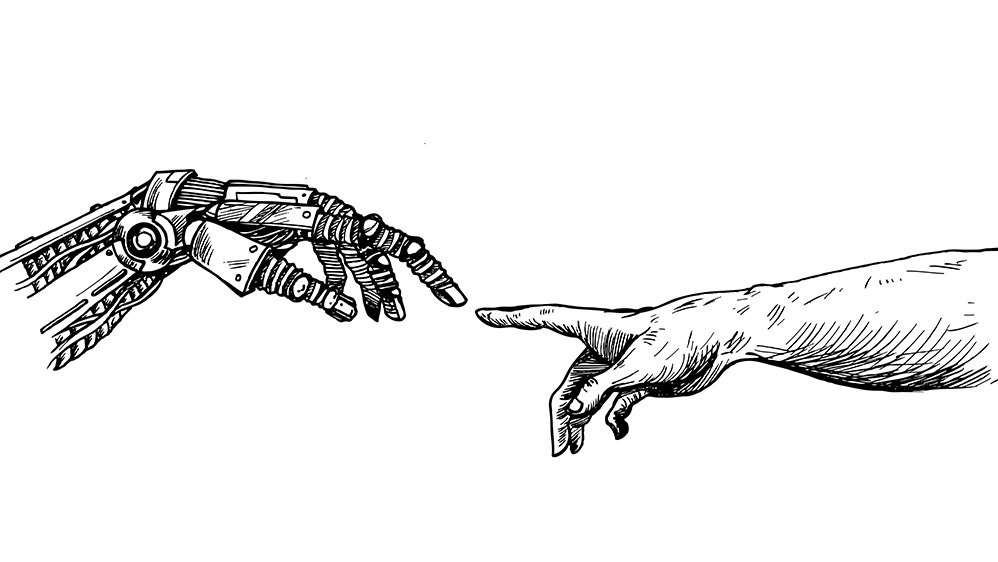“鼻を持ったAI”が立ち向かう、この無臭なる社会
2022.6.10
監 修
株式会社Laboro.AI マーケティング・ディレクター 和田 崇
概 要
動画や画像など、目に訴える情報に溢れた視覚偏重の暮らしが当たり前になる一方、嗅覚には解明されていない部分が多く、ニオイはデジタル化に大きな遅れをとっている分野とも言われます。ですが、選択的にニオイを識別するAI搭載のハードウェアの実用化が徐々に拡大しているほか、虫や動物も含めた生物共通の嗅覚メカニズムに関する研究も進んでおり、AIの開発においてもこれまでと全く別のアプローチが可能になるのではないかという期待感が高まっているようです。画像技術の進歩によって“目を持ったAI”が視覚の分野を発展させているように、“鼻を持ったAI”がもたらすニオイによるコミュニケーションの時代が目前に迫ってきました。今回は、そんなニオイの世界に足を踏み入れてみたいと思います。
目 次
・ニオイは命をつなぐコミュニケーション
・より確実に子孫を残すにはニオイが決め手
・嗅覚系のニューラルネットワーク
・視覚と嗅覚
・E-noseが活躍する命の現場
・古くて新しい診断方法
・症状が出る前に、ニオイが出る
・ニオイのデータから病気を診断するAI
・デジタル化の反動
ニオイは命をつなぐコミュニケーション
より確実に子孫を残すにはニオイが決め手
日本人というと「フィッシュピープル」とか「醤油くさい」などと外国では言われてしまうことがあるそうです。悪口を言われているのかというとそうでもなく、海外から戻って母国に帰り立った日本人が「だしの香りがする」「醤油のニオイがする」と、感受性豊かに懐かしい気持ちを得るような仕草から言われることもあるようです。
とはいえ“ニオイ” があまり良いイメージを持たれにくいのは、ニオイがしないほうが清潔であると好まれ、芳香剤や柔軟剤までもスメル・ハラスメントとして嫌悪対象になってしまうなど、私たちが住む現代の環境が “無臭化社会” へと突き進んでいるからなのかもしれません。
しかし、まだ目の見えない赤ちゃんがお母さんの乳輪腺から出るにおいを頼りに母乳にたどりつくことに代表されるように、元来私たち人間はニオイを嗅ぐだけではなく、自らのニオイを使ってまるでコミュニケーションを取るかのように命をつないできた生き物なのです。

その他にも「女性は遺伝子的に合う男性をニオイから嗅ぎ分けられる」という話があります。これは、白血球の血液型として知られるヒト白血球型抗原の遺伝子タイプが自分とは大きくかけ離れているほど自分の遺伝子とかけ合わさった時に多様性が広がり、より確実に子孫を残すことができる、こうしたことを直感的に感じ取り、特定の異性のニオイを「いいニオイだ」と感じるからだと言われています。
このような生物学的な説からも感じられるように、ニオイは生物にとって最も原始的で基本的な感覚であり、突き詰めていくと人も、犬も、ハエもニオイの情報を同じように処理していることがわかっています。そして、原始的なシステムである嗅覚系回路の正体を解き明すことができれば、脳の未知の領域を理解することへとつながり、人工的な知能、つまりAIを次の段階にレベルアップさせられるのではないかと考える科学者も出てきているのです。
嗅覚系のニューラルネットワーク
視覚と嗅覚
AIが得意なこととして、ある特定の対象物を認識・識別することが一つだと言われます。例えば画像を識別する場合には、その対象がどのように縁取られているか、どんな色か、あるいはどんな質感かなども含めて、RGB値で表現されたピクセル単位の小さな情報が統合され、結果として「猫の顔」といった一つの一般的な概念として識別されます。
一方、ニオイの識別はというと、画像のように標準化された基準や構造がない上、分子の種類や濃度も多種多様で捉えどころがなく、何が似ていて何が似ていないのか、こうした判別・評価がしにくいことは想像に難くありません。
私たちの嗅覚機能は、ニオイが感知されて脳内の神経細胞にその情報が伝わると、ほんの一部の最もアクティブな神経細胞が発火し、それをタグとして何のニオイかを導き出す仕組みになっています。つまり、小さなパターンを統合して答えを導き出す「見る」メカニズムとは異なり、言ってみれば“木から森を見る”ような個を統合して全体を見るアプローチが視覚のメカニズムであるのに対して、“森から木を見る”ような全体から際立った個を見るアプローチが嗅覚のメカニズムということでしょう。

例えば、多品種のリンゴが混じり合ったニオイを嗅いだとしても、私たちはそれが「リンゴのニオイだ」とわかるはずです。対照的に、モザイク画像のようにピクセルがランダムに混じり合った画像からは、私たちはそれが何なのかを認識することができません。
このように嗅覚の神経回路に関する理解を深めていくと、視覚とは別のアプローチで回答にたどり着いたり、これまでの方法ではたどり着けなかった回答を導き出せるかもしれないという考えが湧いてくることは、なんら不思議ではありません。そして、こう考えたかどうかは別として、ハーバード大学とコロンビア大学の科学者が嗅覚にヒントを得た人工ニューラルネットワークを構築したのは昨年のことです。

暑さの厳しい季節にもなると、ちょっと目を離した隙に食べ物にハエがたかっていることがあります。この科学者たちが目をつけたのも嗅覚に関する研究の最先端にあるキイロショウジョウバエの嗅覚系回路でした。
キイロショウジョウバエの触角がニオイに反応すると、特定のニオイを感知する受容体が備わった神経細胞がニオイ分子を電気信号に置き換え、嗅覚系回路の次のレイヤーに送ります。このレイヤーは3層構造になっており、2層目のレイヤーは1層目のレイヤーよりも少ない神経細胞で構成されていて、伝達される情報を圧縮するような役割をもち、3層目のレイヤーはより多くの神経細胞が集まった構造になっています。神経回路のつながり方はランダムで、決まったパターンがあるようには見えません。

科学者たちは、1層目のインプットするレイヤー、2層目の圧縮するレイヤー、3層目の拡張するレイヤーという構成に倣って、神経細胞もショウジョウバエと同じ数にした人工ニューラルネットワークを構築しました。
そしてこのニューラルネットワークにデータを割り当て、ニオイを分類するように命じると、ほんの数分でキイロショウジョウバエの脳と同じように動き出したことが報告されています。中でも、3層目の拡張レイヤーにある神経細胞の1つずつが2層目の圧縮レイヤーの神経細胞と平均6つずつ接続するという、ショウジョウバエの脳で起きていたことと同じことが人工ニューラルネットワークでも確認できた点が、研究に新たな命題を与える発見になったそうです。
E-noseが活躍する命の現場
人間にはおよそ350のニオイを受け取る受容体があり、ニオイを構成する分子がそれぞれに結合する受容体との組み合わせによって、私たちが嗅ぎ分けられるニオイの種類は何兆にも及ぶのではないかと考えられています。
こうした嗅覚の研究は90年代に嗅覚受容体の遺伝子が発見されてようやく芽が出た分野だということもあって、すでに “目を持ったAI”と比べると“鼻を持ったAI”にはまだなりきれていない段階にあり、五感の中では最もデジタル化が遅れている分野とも言われます。加えて、文化的にも無臭化が受け入れられていくに従って、ニオイに関する研究やその重要性が認識されにくくなっているだけでなく、あまりにも膨大な情報が聴覚や視覚から流れ入ってくることがより人々をニオイの存在から遠ざけているようにも感じれられます。
ですが、改めて世界を見てみると、ニオイを合成したり感知したりするセンサーなどのハードウェアの需要は2020年にUSD17.9 million(およそ23億8千万円)であったのが、2027年にはその倍以上のUSD 39.1 million(およそ52億1千万円)に成長すると見られています。

さらに、オランダやイタリア、アラブ首長国連邦では、特に廃棄処理など危険性の高い環境での包括的なE-noseのネットワークが構築されています。また、無作為にニオイを取り出してそれが何のニオイであるかを完璧に識別することはできないにしても、1種〜10種程度の特定のニオイを識別するAI搭載のハードウエアの実用化が進んでいます。
危険を伴う廃棄物処理の現場や最新の兵器が使用される戦場、あるいは命に直結するような水質管理や医療など、さまざまな分野から“鼻を持ったAI”がこれまで難しかった問題に新たな解決アプローチで挑んでくれるのではないかという期待が寄せられているのです。
古くて新しい診断方法
症状が出る前に、ニオイが出る
医学の目覚ましい発展により、日本では女性の2人に1人が90歳まで生きられる時代になりました。病気を早期発見できるようになった医療技術が私たちの寿命に与えるインパクトは大きく、血液検査や遺伝子検査などさまざまな検査で病気が判明することが当たり前のように受け止められています。
しかし、実際には検査で判明しない病気もまだまだあり、そういった病気の場合、初期症状や兆候などが判断材料となることから、病気が進行して明らかな症状が発現するまでは診断が下されないケースも少なくありません。

パーキンソン病も検査で判明しない疾患の一つでしたが、2020年に一人の女性が「ニオイでパーキンソン病を嗅ぎわけることができる」としてメディアに取り上げられたことで、早期発見に向けた新たな領域に入りつつあります。
女性がはじめてそのニオイを感じたのは、医師である夫がパーキンソン病だと診断される14年も前のことだったそうです。そのニオイがパーキンソン病と関わりがあるかもしれないと疑うことになったのは、診断された夫とともにサポートグループに参加したその女性が、部屋にいるパーキンソン病の人たちから同じニオイがしてくることに気づいたからでした。
夫妻はエディンバラ大学のパーキンソン病の研究者にそのニオイのことを伝えに行きますが、当初は「神経の疾患にニオイがするはずがない」と受け入れられなかったそうです。
半信半疑でパーキンソン病の患者とそうでない患者のTシャツを彼女に嗅がせる実験が行われたところ、彼女はほぼ100%の確率でパーキンソン病の患者のTシャツを言い当てます。ただ、その中で1枚だけ彼女がパーキンソン病でないのにパーキンソン病だと主張したTシャツがありました。研究者を驚かせたのは、実験からかなりの時間が経った後、パーキンソン病だと間違われた人が本当にパーキンソン病を発症し、その診断が下されたことでした。
ニオイのデータから病気を診断するAI
研究は進み、今ではパーキンソン病の患者は皮脂の中に特有の揮発性有機化合物を含んでいることがわかっています。そして、その皮脂を “嗅ぐ” ことによってパーキンソン病を診断するシステムを開発している科学者もいます。
中国の浙江大学では、クロマトグラフィーやセンサーなどを用いて皮脂サンプルの化合物を分析することで揮発性有機化合物を特定し、その情報を機械学習のアルゴリズムに投入するという方法で、ニオイからパーキンソン病を診断するAIの研究が行われています。この研究では、サンプルデータとしてパーキンソン病患者31名とパーキンソン病ではない人32名の皮脂のデータ用いて、それぞれの状態を識別するアルゴリズムが開発され、発見されたうち特に顕著な3種の揮発性有機化合物をベースにしたアルゴリズムをさらに用いることで、70.8%の正解率(accuracy)でパーキンソン病を診断することが可能であることが報告されています。
この70.8%という数値をもう少し掘り下げると、実際にパーキンソン病の患者がその通りに検知された正解率(真陽性率:true-positive rate)は91.7%、パーキンソン病でない人がその通り検知された正解率(真陰性率:true-negative rate)は50%だったとのことです。

健康な細胞が攻撃されるとそれを代謝する中で副産物が生まれ、その副産物が血流に乗り、息や汗、尿によって排出され、そこに含まれる揮発性化合物によって感染しているかどうかがニオイとして感じ取れる−−、このメカニズムは神経の疾患であろうとウイルスによる疾患であろうと、さまざまな病気に通じるものです。
「もっと早くわかっていれば…」という遣る瀬無い思いを減らしてくれるのは、実はこれまで私たちがせっせと消すことに一生懸命になっていた口臭や体臭という、とても基本的な健康バロメーターの存在によるものなのかもしれません。生活に溶け込むようにして、“鼻を持ったAI”が息や汗のニオイから病気を探知するような未来が少しずつ見えてきています。
デジタル化の反動
本来は快・不快によって使い分けられるべき「匂い」と「臭い」が同じような言葉として用いられているほか、自然のニオイに囲まれた生活から離れつつある子どもたちの中には本物の花の香りを「トイレの芳香剤のニオイだ」と言う子もいるそうです。画像や音の領域で技術精度がこれほどまでに高まった現代であっても、なぜか人工のデジタル・ワールドと実際のリアル・ワールドに隔たりを感じてしまうのは、ひょっとしたら元来、生物の命と直結していたニオイの要素が失われつつあるからなのかもしれません。
デジタル化によってますます生活からニオイが消えていく一方、これまで「見る」ことにフォーカスが置かれていた博物館や美術館で「嗅ぐ」ことを取り入れた取組みも進められているといった話もあり、ロンドンでは数百年前の本など、アナログなもののニオイを再創造する研究もなされているそうです。

嗅覚を持ったAIがスマートフォンに実装されて一般社会での利用が始まったとき、人々は自然とポケットからニオイのメッセージを取り込んでいく––、こんな世界がやってくるとしたら、私たちはきっと現代の “無臭化社会” をどこか物足りない時代だったと振り返るに違いありません。
今ではあまり見かけなくなってしまいましたが、『世界の空気缶』という空気だけが入った缶詰が土産品として楽しまれた時代がありました。そして現代、生活の中ではニオイを避けていながらも、猫の体に顔を埋めてニオイを吸い込むことが「猫吸い」といって受け入れられていたりもします。
インターネットも電気もない時代から培われてきた私たちが本来的に持っている太古の感覚、“嗅覚”が失われることはこの先もしばらくはないはずです。理屈のいらないコミュニケーションから得られる快感を、AIをはじめとするデジタル技術を活用することによって取り戻すときが来ています。